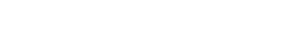/////////////
World Heritage Management
白川村
「遺産は保護するだけでは護れず、訪問者がその正しい意味と重要性(=significance)を理解できるよう、遺産に積極的にアクセスできる管理手法をとることが必要である」とICOMOS国際文化観光憲章(1999)は述べている。遺産保護に大衆レベルでの高い認識と支持がない限り、政策的にも資金的にも管理し続けることはできないという重要な事実に対する認識がそこにある。ここには、観光客を「遺産の高潔性やとりまく環境を物的に脅かすもの」と捉えていたICOMOS文化観光憲章(1976)からの大きなパラダイムシフトを読み取ることができる。 欧州に限らずアジアの世界遺産を見ても、有名遺跡では立派な公園化が進み、それらを政府やNGO等の公益機関が運営して博物館やガイドシステムを充実し、十分なインタープリテーション(遺産の解説)の対価としての観光収益を、遺跡保護や地域社会に還元するシステムが構築されてきている。しかし、こうした遺産の多くは、地域社会の人々の暮らしから切り離された考古学的遺跡であることが多く、筆者が専ら関わってきた歴史的な集落や町並み、旧市街地といった遺産地域の保護=マネジメントについては、未解決の課題が山積みであると言ってよい。 近年ユネスコは、こうした人々の生活と共に生き続ける空間や環境の総体としての遺産を「リビングヘリテージ」と呼び、とくにアジアにおいてこの種の遺産を保護する必要性を説いている。リビングヘリテージにおいては、有形・無形を問わずその遺産の所有者が多岐にわたるため、上記のように観光収益を公益化する利害調整やシステムづくりがきわめて難しい。また、遺産の重要性の相当部分が地域社会の人々の暮らしに内在(潜在)するため、観光客は容易にその価値の理解にたどり着けない。こうした課題をマネジメントできないままに観光化が進むと、遺産はその価値を、そこに住む人々の暮らしと共に失うことになる。悲劇である。 日本の例を挙げれば、白川郷の合掌集落がある。数百年間その土地を耕し、山稼ぎをしながら綿々と住み続けてきた人々が、自らユニークな住宅建築様式として完成させた合掌造り家屋とともに今日まで生き続け、「結」の仕組みによってお互いの家屋の屋根を真正な姿で葺き替える習慣をまもっている。里山や水田、畑、畦道と水路、寺社や社叢からなる集落空間には、どぶろく祭が毎年執り行われる。まさに文化的空間に無形遺産が表現されるなかで遺産の真正な価値がまもられているリビングヘリテージである。 今日とは異なり、1995年の白川郷の世界遺産登録は、住民や自治体が求めたものではなかった。1992年の日本政府による世界遺産条約批准によって、城や寺院といった宗教や権力の象徴が文化遺産として登録されるなか、白川郷の合掌集落は、日本の民の文化の象徴として、登録されることが不可欠な遺産であった。登録は国策であったと言ってよい。その一方で、やはり国策として東海北陸自動車道が計画され、2008年7月に全線開通した。遺産登録前には50~70万人で推移していた観光入り込み客は、今や200万人を超えようとしている。 こうした状況下で、約600人の白川村の遺産地区住民は、この1年間で16回の住民代表(30名)による検討会議とその成果を住民代表自らが住民に説明する説明会を7回にわたり開催し、世界遺産を自らマネジメントするためのマスタープランを内発的、自律的に策定しようとしている。 住民の手の内にあってこそ生き続けられるリビングヘリテージだが、実は既に、60年代から展開してきた日本の町並み保存運動の中に、経験と英知の蓄積がある。これからの日本による遺産保護の国際協力には、ここに大きなテーマが眠っていると考えている。 (「遺産と観光の持続可能な関係づくり 『トンボの眼』2008年より)
/////////////
明治日本の産業革命遺産
原稿執筆中
/////////////
長崎教会群
原稿執筆中
/////////////
北の縄文
原稿執筆中
/////////////
阿蘇
原稿執筆中
/////////////
錦帯橋
原稿執筆中
/////////////
ヨルダン
原稿執筆中
/////////////
エチオピア
原稿執筆中
/////////////
ペルー
原稿執筆中
/////////////
フィジー
原稿執筆中
/////////////
世界遺産 アルベロベッロ/南イタリア
「短い建築サイクルが結実させたデザイン」
誰が見てもユーモラスな景観だが、この屋根のデザインが誕生した経緯には笑えない逸話がある。 もともと石だらけの貧しい農村であったこの地に、15世紀末、ナポリ王はとある伯爵を送り支配させる。 当時の徴税は家の戸数に比してなされたため、王への上納を渋った伯爵は、いつでも壊せる家造りを住民に命じ、 国の役人が来るたびにわざと壊させたという。がれきの前で「これは家ではない」という住民の言を役人が ほんとに信じたかどうかは別として、筆者は次のような面白い想像をしてみた。
こうしたくだらない命令に繰り返し従う屈辱を、いかにストレスフリーで乗り切るかということを 前向きに考えた住民もいたはずである。その期間たるや、圧政が終わる18世紀末までの300年である。 壊しても壊しても、再建に新しい建材の調達が要らない構造にできないか、これは最大の関心事であったろう。 皆同時に施工する以上、他人の手は借りられないとすれば、家族で施工できる造りや規模にデザインは収斂する。 また、せっかく再建するのだから、従前と全く同じじゃつまらないし、隣の家よりも格好良く造れないか、 ということも常に考えたろう。こうして世界遺産になるべき高度なデザインは結実した。繰り返す建て直しが 宿命と諦めれば、ただ暗澹とことをこなすのではなく、一つのイベント的盛り上がりもあったかも知れない。 どこか白川郷の「結い」による屋根葺きと通ずるものを感じた。そう、ここは白川郷と世界遺産の姉妹都市提携をしているそうだ。